老人医療NEWS第43号 |
本年は、介護保険法施行準備の最終年度となります。介護報酬や認定基準、保険料算定等々一応の議論は進んでいますが、詳細設計を含め本年には、すべての事項を決定しなければなりません。さらに市町村等においては、各種介護事業の準備を進める必要があり、例えば地域住民に対する本制度の説明、在宅サービスや施設サービスの事業者候補への説明や指定、実際の保険料の算定等その事務量は膨大になってきています。
誰もがこれまでの介護制度では問題があると感じながら、実際に保険料を徴収し始めた時には、様々な意見や批判が出てくることが予想されます。そうした地域住民の声を最初に受け止めるのは市町村役場でありますから、そうした苦情相談とも言える処理にも苦労があると思います。
かつて国民皆保険が成立した時に「何時でも、何処でも、誰でも良質の医療を受けられる」ことを目標としたと同じで、介護保険も「良質の介護を受けられる」ことを最終目標にしています。従って、保険あってサービスなしと揶揄されるような状況は、何としても避けなければなりません。
一方、老人医療改革も大きな課題です。薬価制度の改革や、診療報酬制度の改革そして高齢者医療制度の改革が求められています。薬価制度は「薬価差の縮小・解消」を、また診療報酬制度は「コストと対応した制度」「出来高の是正」などが、また高齢者医療制度は「拠出金制度の見直し」が論点となっています。
老人医療の観点から言いますと、診療報酬体系を一般と老人に分けている現行体系は、果たしてこれでよいのかということがあります。介護保険が施行されても、老人医療は慢性期医療を含め重大な問題です。これまでは、老人の疾患特性を勘案し、入院については包括を幅広く、また外来はプライマリケア機能を、と言った基本理念を検証し、今後どうするか検討する必要があります。包括制と老人医療の質の問題、そしてプライマリケア機能の総点検が必要です。どうせ抜本改革するなら、もっと掘り下げて、21世紀にふさわしい体系とする必要があります。
この意味で、貴会の御意見も頂戴したく考えております。貴会の益々のご発展を祈念しております。
折りたたむ...高齢者医療供給体制のありかた
「老人医療」はこれまで「慢性期医療・長期療養」に主眼が置かれ、急性期は今までの医療、一般医療と同じでよしとされてきた。
しかし今、老人医療があまりにも介護にシフトした対応となっている。そのため合併症を起こしてからの、また、障害が生じてから(寝たきりになってから)の後始末の、後片付けの医療として老人医療が位置付けられている。すなわち入り口の整理(寝たきりを予防しながらの治療)がなされないままできているのである。
今までの手法(救命・延命、疾病医療。治療が終ってからのリハビリテーション)では高齢者ほど治療効果は不確実であり、かつ医療費はかさみ利用者の満足度も低い。また、現在の高齢者の医療ニーズは決して延命、救命といった肉体的生命への集中対応だけでなく、精神的生命、社会的生命、文化的生命への配慮を重視した、むしろQOLをもっと重視しつつ、寝たきりを予防していく多様なニーズへと変容してきている。
今まさに医療における費用対効果を直視すべき時期にきているのではなかろうか。
昭和医科大学救命救急センター講師の刑部義美氏は「救命救急センターに搬送された80歳以上の患者155例を対象に予後を検討した。患者の原疾患は、循環器系、脳神経系、呼吸器系が約8割を占める。センター退出時は、生存52%、死亡32%、死亡到着16%とで生存率は高いものの、自院、他院の専門診療科や自宅に移送後、日常生活機能精神的機能が低下するケースが生存者の約9割にみられた。また、生存者の半数以上が数週から数ヶ月の間に死亡、残りも寝たきり、植物状態になるケースが多く、日常生活が可能な状態まで回復したケースは生存者のわずか2.5%だった。センター搬送時から退出時までの医療費は、一人当たり約167万円。若年者の治療では50万円以上かかるケースはまれで、高齢者の集中治療は高額の医療費に対して治療効果は低いという結果が得られた。」と救急医学会で報告されている。
しかしこれからの時代の趨勢として一般病院の平均在院日数は極端に短くなり、急性期治療(救命・延命・疾病医療)の施設として特化していき集中治療化が進められてくる。
このような集中治療化、重装備化は高齢者にとっては限界があるが、かといって介護保険で高齢者のすべての医療を診ていていくのもあまりにも片手落ちである。したがってこれからの高齢化社会における高齢者にふさわしい、ニーズにマッチした、かつ効率的な新たな医療供給体制の構築が早急に整備される必要がある。
これからの高齢者にふさわしい医療は予防医療であり、早期発見、早期治療とともに合併症・他臓器症候群への予防・予測的医療を行いつつ、障害(寝たきり)を未然に予防していく、日常生活への支援を少しでもなくしていく医療であらねばならない。そのためには医療供給体制における入り口(救急医療、プライマリーケア)の整備、変容が高齢者のためには必要となる。そして医療も介護と同じく、生活者への視点を重視し、在宅医療を中軸としたコミュニティケアに基本理念が置かれるべきである。
社会保障共通の基本理念(利用者が主体)の構築により、社会サービス全般の継続性・一貫性が担保されなければならない。
地域にセイフティーネットの構築を
24時間、365日居宅における安心、安全を利用者(患者・家族・介護者)に保障していく医療体制が地域での在宅医療を保障していくセイフティーネットとなる。
地域(圏域)を病棟ととらえ、医療機関をナースセンター(核・拠点)として位置づけ、いつでも要請にこたえ医療スタッフが適時活動していく組織・チームを編成する。そして呼ばれれば当然ベッドサイド(居宅)にいくこともあれば、ナースコール(電話対応)ですむ場合もあろう。看護婦あるいは医師が出勤することもあろう。
居宅での医療の限界もあろうがあくまでも利用者の意向が優先される。あるいは緊急入院して高齢者にふさわしい医療(リハビリテーションを含めたトータルケアサービス)が提供されることもあろう。また、高次・専門医療機関へ搬送されることもあろうが、とりあえずはこの地域でのセイフティーネットを通過していくシステムの確立が必要である。
このセンターを「在宅医療支援センター」と呼ぼう。在宅医療支援センターは当然24時間、365日医療相談に応じられ、かついつでも訪問看護、往診体制が組み込まれ、緊急入院のためのベッドも用意されている必要がある。
スタッフとして有床診療所、病院の基準(ハードは当然高齢者にふさわしい療養環境が要求されよう)に加え、充分な介護要因とともにリハビリテーションスタッフ、ケアマネジャーといったトータルケアサービスを保障していく専門職も欠かせない。
報酬体系は当然医療保険に位置付けられ、定額制で期間の限定もあってよい。ベッド数も多くは必要ない。
そして地域の各かかりつけ医は在宅医療支援センターと有機連携していく契約関係を結び自己完結から地域内完結へと機能アップしていく。
これからは個々の医療機関ごとに、しかも医療機関内にセイフティーネットが架けられるのではなく、地域の居宅にまで展開したセイフティーネットの構築が求められているのである。そして地域のかかりつけ医、介護サービス事業者、介護施設と、セイフティーネットとが連携して居宅での高齢者や要介護者への医療・安心・安全を保障していきつつ、寝たきりを予防していくことが必要となる。
今まさに原点に立ち返り、医療供給体制の根幹をなすプライマリーケア体制(セイフティーネット)の確立が不可欠ではなかろうか。
折りたたむ...当会主催の特別講演会が平成10年11月19日、ダイヤモンドホテルにて約60名が参加して開催された。演者は日米両国の正看護婦の資格を持ち、15年間に亘ってサンフランシスコで仕事をされ現在、医療コンサルタントとして御活躍の小林明子氏であった。
大塚会長の挨拶に引き続いて行われた講演で、小林氏はまず米国の健康保険制度(公的保険メディケア、メディケイドとHMOなどの民間保険)と医療費の支払い方法について概説した。その中で民間保険会社は決して損をしない仕組みになっていること、高齢者長期医療も出来高からDRG導入による定額払いになっていることを強調した。次いで米国での老人医療についての話題におよび、老人に対しても入院期間の短縮化と在宅医療の促進が行われていることが紹介された。老人医療の構成および流れとしては図のようになる。
スキルとはナース、PT、ST、OTなどの資格を有する者が提供するサービスを指し、OTはこれに含まれておらず、ホームケアにおけるナースの仕事は患者が自分で自分のケアができるように指導することに限定されているとのことであった。
さらに「オン・ロック(On・Lok)と呼ばれる、サンフランシスコのチャイナタウンでの包括的高齢者ケアプログラムが紹介された。これは送迎デイケアが中心であるが、ホームヘルパーも派遣される。なお、LTC(ナーシングホーム)におけるケアの質の低下も深刻な問題であるらしい。
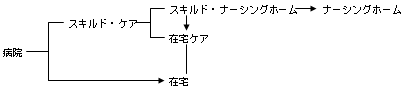
平成11年2月13・14日、都内で当会主催の「平成10年度第2回医師ワークショップ」が開催された。医療保険福祉審議会が「痴呆性老人への身体拘束禁止」を公表したことから議論が盛り上がった。
その中心的問題は、点滴、中心静脈栄養、経管栄養時の抑制をどう考えるかといったことであった。縛らないで実施する工夫も紹介されたが、「そもそも栄養補給量がいいかげんだ」という意見もあった。高齢者の最大の栄養問題がプロテインとエネルギーの低栄養であることは同意できても、どのように対処するのかはバラバラということだ。
老人専門医療において栄養は重要な問題である。当会加入病院が強力してきた「高齢者の栄養管理サービスに関する研究」(主任研究者、国立医療・病院管理研究所松田朗所長)では、低栄養状態のスクリーニング指標として血清アルブミン値1デシリットル当たり3.5グラム以下を採用している。そして老人専門病院入院患者の40%程度が検討の対象となる。
問題は、院内で安静時エネルギー代謝(Resting Energy Expenditure)を簡単に測定することができなかったことである。これについては測定時間が3分間ですむスグレモノがすでに開発されている。個々の人のエネルギー量が判断できれば1日当たりの補給量が判断できることになる。このREEから計算すると男性では最小475から最大2,253キロカロリーと差があることも分かっている。どうも1日1,500キロカロリー前後の設定自体を患者別に見直すことも必要となっている。
これらの研究成果について下記の本が出版された。勉強することを勧めたい。
細谷・松田監修、小山・杉山編「これからの高齢者の栄養管理サービス」
第一出版株式会社、A4版、361ページ。定価4,000円+税。
注文は直接出版社へ(TEL:03−3291−4576)
| ×閉じる |