老人医療NEWS第37号 |
今や、保健・医療・福祉の連携、再編成・統合が関係者の合い言葉のようになっている。しかし、20年、30年前に、今日のような状況を予想した人がいたであろうか。当時、医師は診療所を開業しても、病院を開設しても余程のトラブルでもない限り高収入を得ることができたし、医師であるというだけで他の医療従事者の頂点に君臨することもでき、施設内の医療だけに執心していればよかったのである。
ところが、医療を取り巻く情勢は一変した。人口構造・世帯構造・疾病構造の変容と生活水準の向上に伴う保健・医療・福祉ニーズの多様化、国民医療費・特に老人医療費の増大、医療従事者の専門分化と身分意識の高まり等々に対応するため、厚生省は関係法律の制定・改正に腐心してきた。
例えば、老人保健法の制定(保健と医療の一体化)と改正(老人保健施設の創設・老人保健計画の一体化による老人保健福祉計画の導入、老人訪問看護の制度化等)、医療法の大改正(医療計画の導入による病院病床数の規制等、特定機能病院・療養型病床群の制度化による医療施設の機能分化等)、保健所法の改正による地域保健法の制定(保健所業務の見直しと市町村保健センターの法定化による地域保健体制の再構築等)、健康保険法の改正(訪問看護事業の拡大と在宅医療の推進による施設内医療から在宅医療への誘導、保険給付の包括化と特定療養費制度の拡大等)である。
これらの一連の法改正等により、全国の9700余りの病院は、それぞれの思いを込めて、提示された道(各種の医療施設)を選択してきた。例えば、先述の施設のように法定化されてはいないが、診療報酬上位置づけられた施設として、特例許可老人病院(介護力強化病院等)、紹介外来型病院、開放型病院、特定承認保険医療機関、特定疾患療養病棟、精神療養病棟、老人性痴呆疾患治療病棟、緩和ケア病棟がある。
これらの施設が将来どのような運命を辿るのか、例えば、患者をはじめ国民のニーズに応えている施設が栄えるような保険点数化が講ぜられるのか、保険財源の御都合主義に左右されてしまうのか、大いに心配である。
願わくば、最初に国民の声、次に保健医療福祉関係者の熱意、そしてこれに応える行政側の智恵(政策)、最後に政策を支える保険施策であってほしい。
折りたたむ...ヘルスケアシステムの確立をめざす
医療法人近森会では、急性期病院である近森病院・精神科の近森第二分院・近森リハビリテーション病院の3病院が機能別に編成されており、JR高知駅から徒歩5分、はりまや橋から徒歩7分の高知市中心街に位置しています。
近森リハビリテーション病院は、昭和61年に計画され3年半を費やして平成元年12月にオープンしました。当時リハビリテーションは非採算部門であると言われていましたから、民間のリハビリテーション専門病院の開設は馬鹿げている、3年はもたないとも言われたものです。しかし開設から6年半が経過して経営は何とか軌道に乗ってきました。
対象とする疾患は主として中枢神経疾患(脳血管疾患・頭部外傷・脊椎損傷・神経筋疾患)ですが、
- 発症からできるだけ早く入院を
- できるだけ早く自立を
- 入院期間は短く
- あくまで自宅復帰をめざす
従来リハビリテーションと言うとPT・OTがその代名詞のように言われていましたが、当院ではリハビリテーションの中心は看護であり、実践は多職種参画のチームアプローチで行うとのコンセプトで運営していることが特徴と思われます。
145床を3フロアーに分け、重度・中度・軽度の3段回のPPC(Progressive Patient Care)システムを採用し、医師・看護婦・介護職員・PT・OT・ST・MSWが各フロアー専任体制をとり、ケアプランはMDSやケアパッケージではなく従来の看護計画に頻回なリハビリテーションカンファレンスを加えた形態をとり、カルテは全職種を一元化しビジブルを使用するなどチームアプローチに有利な工夫をしています。
看護体制はかつて基準看護特Ⅱ類でしたが、新看護(3対1・6対1)に移行、さらに平成7年から療養Ⅰ群入院医療管理料、平成8年からは療養Ⅱ群入院医療管理料へと移行しました。しかし対象が重度なため規定の看護要員数では足りず大幅な人員増をはかって運営しています。
入院患者は年間約500名、平均在院日数は90日であり、外来は1日120人で、通院患者の80%にPT・OT・ST等が提供されます。
在宅訪問活動は昭和62年から開始し、現在は訪問看護ステーションちかもりと在宅介護支援センターえのくちが機能していますが、訪問対象者の増加とともにスタッフも増員し、約120例に対して1ヶ月に約800件(訪問看護:訪問リハビリ=7:4)の訪問を実施するようになっています。
重度の在宅高齢障害者は、訪問活動だけでは閉じこもり症候群となり、家族も含めてQOLの低下を招くため、ショートステイを近森リハビリテーション病院で対応していましたが、患者数の増加にともない、平成5年12月にショートステイの受け入れ先として老人保健施設いごっぱちを開設しました。36床と小規模ですが平均在院日数は17日と全国との比較では極端に短くなっています。寝たきり度はB・Cランクがデイケア:73%、入所:80%を占め、リハビリ病院と同様に重度が多くケアスタッフも規定の倍近い人員とせざるを得ませんが、いわゆる在宅支援型老人保健施設として機能しています。
以上の近森リハビリテーション病院・訪問看護ステーションちかもり・在宅介護支援センターえのくち・老人保健施設いごっぱち・近森病院のリハビリ部を併せて近森リハビリテーショングループと称し、急性期リハビリを近森病院で、回復期リハビリを近森リハビリテーション病院で、維持期リハビリを訪問看護ステーションちかもり・在宅介護支援センターえのくち・老人保健施設いごっぱちで提供するシステムをとっています。
現在、訪問看護ステーションちかもり・在宅介護支援センターえのくち・老人保健施設いごっぱちを1ヶ所にまとめ、これに近森リハビリテーション病院の外来を移設し、配食サービスセンター・テクノエイドセンターを加えて、在宅総合ケアセンターとして機能するべく準備中です。
折りたたむ...21世紀といっても、もはや4、5年後になってしまってすでにあまり使われなくなっている感があります。以前は21世紀というと夢いっぱいのSFの世界を勝手に描けば良かったわけですが、今回は、ある程度予測しうる2005年はいったいどんなことができる時代になっているのだろう、というのが話のきっかけです。
まずこんな事があったらいいなと思う第1番目の出来事は、長生きの家系が確立されることです。明治になって戸籍制度が確立されて150年としますと、親子、孫3代にわたる長生き家系が出てきても良い頃だと思います。おじいさんもおばあさんも100歳まで生きたし、おとうさんもおかあさんも100歳を越して、子供たちも皆100歳代だ、なんて家系が出てきたらとても面白いことだと思います。どこが面白いかと言いますとひょっとしたら長生き遺伝子が見つかるかもしれないからです。
現在遺伝子の世界で言われていることは、遺伝子のある一部に寿命を決める場所があるらしいということです。その部分をテロメアというのですが、年を取るとこの部分の長さが短くなるというのです。1990年にシルビア・バジェティーさんが言い出したことですが、最近は大方当たっているらしいということが証明されつつあります。また最近ではテロメアを作る酵素も寿命に関係していると言われています。
しかしこのようなことは実際に人ではどうなっているのかとか、長生きの家系ではどうなっているのかとか、若しくはこれとは全く関係のないものが長生きには大切だ、などということが解ってくるとなんだか愉快な気分になってきます。多分長生き家系が確立される頃にはヒトのDNAのすべての配列を決定しようとするヒトゲノムプロジェクトも少し進んでいることと思います。そうなれば長生きの家系のDNAと、普通の家系のDNAとどこが違うかも解ってくるかもしれません。ひょっとして本当に長生きな遺伝子なんてものが見つかるかもしれません。多分これは私の勝手な想像ですが本当は長生き遺伝子なんてないんだろうなと思っているのです。ただ長生きする人の遺伝子は壊れにくかったり、壊れてもすぐに元どおりに直す力が強かったりするのではなかろうか、と考えている次第であります。要するに打たれ強い遺伝子を持っていれば長生きできるであろうというのが我々の想像です。
こんな事が何で2005年の老人医療かと言われる方も居られると思いますので、最後に少しSFも付け加えさせていただきます。
私どもが遺伝子治療に取り組み基礎研究を初めて早いもので10年が過ぎようとしております。未だにチョロチョロ臨床の合間を縫って取り組んでいますが、今は10年前に比べるととてもやりやすくなってきました。10年前遺伝子の話をしますと医師の中にも、イデンコ(遺伝子の子)なんて呼んでしまう先生もいらっしゃったくらいです。専門家の先生でさえ、ベクター系(遺伝子の運び屋さん)の発がん性の問題やハウスキーピング遺伝子(大切な遺伝子)を破壊するのではないかといった問題や、ベクター系そのものの毒性の問題という様々な問題点を指摘する声が強かったことが思い出されます。でもなんのかんの言っても日本でも遺伝子治療が臨床化される時代になりました。
そこで最後になりますが、2005年までには是非とも遺伝子を打たれ強くする薬が開発されますことを切に願うのであります。これによってヒトは自分で自分の寿命が決められるようになると同時に、コカイン症候群(早老症候群)で苦しんでいる患者さんにも朗報がもたらされる時代が1日でも早く来るように、というところでこの項を終らせていただきます。
折りたたむ...1996年1月22日~1月27日
霞ヶ関南病院 院長 齊藤正身
湖東病院 院長 猿原孝行
はじめに
当会が行う来年度からの海外研修企画のための視察として、一夜漬けの勉強でシドニーへ飛び立ったのは大きな間違いであった。視察には大任を受けた石川誠、齊藤正身、猿原孝行の3名の医師に、コーディネーターおよび通訳としてメディアーク経営研究所所長の須磨忠昭氏に同行していただいた。
外国語は苦手であったにもかかわらず、あまりにも得ることが大きすぎて私の頭の中は混乱してしまった。オーストラリアの国を挙げての保健・医療・福祉のイノベーションに強烈なカルチャーショックを受けて、しばらく自己の頭の中で整理が必要なほどであった。外国嫌いな私ではあるが、オーストラリアなら是非また行きたい、それも観光でなく勉強にである。次回は予習を十分にしてもっとじっくり見て確認したいことが山のようにあると感じている。
今回の視察旅行の目的は、海外職員研修として適当な施設を探すことであった。今まで実施されてきたQEC(クイーン・エリザベスセンター)での研修は、地域(バララット市)全体で作り上げたケアシステムや各専門職の職域を越えたチームアプローチなど、参加者が大きな収穫を自院に持ち帰ることができ、大変有意義な研修だった。今後も何らかの形でQEC研修は続けて行きたいと考えているが、大都市あるいはその近郊で行われている高齢者ケアを勉強する機会を設けたいという要望もあったため、今回はシドニー市内および近郊で研修が可能な2つの候補施設を視察してきた。
オーストラリアにおける高齢者医療のポイント
視察施設はシドニー郊外のホーンズビー・クリンガイ病院とシドニー市内にあるシドニー中央地区保健サービス(以下CSAHS)である。以下ショックを受けた順に項目を列挙し、振り返ってみたい。
- 急性期から慢性期までの、あまりにも一貫しているヘルスケアシステム。
- あまりにも短い急性期病院の平均在院日数(4.8日)
- さらにあまりに短いリハビリテーション病院の平均在院日数(16日)
- 医師ごとに受け持ち患者の平均在院日数が示され、勤務評定されていること。
- デイホスピタルへの通院の期限があること。(60日)
- 老年科医やリハビリテーション専門医の動き(あちこち飛び回っていること)。
- Aged Care Rehabilitation という呼び方。
- 慢性期病棟(日本では慢性期とは言えないが)もナーシングホームも1病棟が26床。
- リハビリテーション病院のトップは看護婦。
- リハビリテーション病院に専任の病棟配属のPT・OTがいること。
- 病棟配置人員規定・配置構造規定は一定のガイドラインのみで明確なものはない。
- 経口摂取ができなくなったら死ぬとき。
- 重度は施設、軽度は在宅の考え方が徹底していること。
日ごろから医療システム・ヘルスケアシステムには興味があり、リハビリテーション医として日本の医療システム・ヘルスケアシステムをどのように構築すれば良いのか悩んでいたこともあり、上記のどれをとっても私の常識を超えた医療システムであった。
特に納得がいったのは6の老年科医やリハビリテーション専門医の動きである。急性期病院からリハビリテーション病院さらにデイホスピタル等を日々あちこち転々と動き回っている印象を受けたが、確かにその方が患者の流れがスムーズとなるであろう。
日本ではすぐソーシャルワーカーの出番となるが、メディカルケアからヘルスケア、そしてライフケアへの流れを迅速にしている要因は、オーストラリアでは老年科医やリハビリテーション専門医の働きがあってこそと思われた。
日本の老年科医やリハビリテーション専門医も、一つの病院内に閉じこもらず、日々転々と医療施設(急性期病院から診療所まで)や福祉施設を回るほうが、より効率的な医療が展開できるのではないだろうか。
そのためにも9のリハビリテーション病院のトップは看護婦であることが必要なのであろう。一昨年欧州のオーストリアの州立医療福祉センターでは、慢性期病院はやはり看護婦がトップであった。慢性期は病棟の管理が主体であり、医師を院長にするより看護婦がマネジメントするほうが実際的ではないかと以前から考えていたが、ヨーロッパもオーストラリアも、すでに実践していることにおどろいた。
10のリハビリテーション病棟に専任の病棟配属のPT・OTが存在していることは、私も全く同感であり、先を越されたとショックを受けた。26床のリハビリテーション病棟にPT・OTそれぞれ1名ずつ、さらに助手が1名ずつ配属されており、病棟内で盛んに動き回っている姿は日本のPT・OTとは異質に見えたが、これぞ入院のリハビリテーションという感じがした。これをきっかけに当院ではより革新的なシステムを6月より実施することにした。
8の病棟1ユニットが26床である理由は質問したがよくわからないようであった。軍隊の1個小隊の数なのか、アルファベットが26文字だからか、いろいろ推測しているが日本の50とか60床はやはり再検討するべきではないかと思われた。
急性期も在院日数が短いが、リハビリ病院も短い、そしてデイホスピタルも期限が決められている。これでは患者や家族から多大なクレームがつくのではと心配であった。しかし在宅ケアにしても、施設ケアにしても格段に手厚いケアの現状があり、我が国の現状を単に比較することはできない。しかし同じ人間社会でありながら、ここまでの差を容認することは断じてできないと競争心を掻き立てられたのは事実である。全体に平均日数は短くとも、ゆったりと流れている印象を受けた。働くスタッフもあくせくしている様子がない。まるで馬車馬のように働いている、自分や当院のスタッフと比較して、恥ずかしさすら感じた。
7のAged Care Rehabilitationの呼称は老人のケアとリハビリテーションが1対のものであると考えられていることを意味しているが、日本もそのように呼ぶようにならないものかと考えた。
病棟の人員配置基準・構造設備基準は明確なものはないとのことであるが、我が国であればどうなってしまうだろうとも考えさせられた。
各病院は決して立派で贅沢なものではない。古い病棟を改造してあちこちに工夫がなされていた。病院のアメニティに関してはさほど見るべきものはなかったと思うが、やはりシステムとシステムを構築する基盤が重要と思い知らされた。しかしその核心に関しては残念ながら触れることはできなかったように思う。この点がもっとも肝心な部分であるのだが。
Aged Care とHome and Community Care Act(HACC法)システムについて
オーストラリアの10年前は高齢者ケアについて極めて貧困な状態であった。ほとんど施設入所であり、このために費用が高騰していた。ケアの内容の選択肢もわずかであり、施設の入所待機者が極めて多かった。したがって高額の有料老人ホームに入るしかなかった。
HACC法により1985年から大きく変化した。現在70歳以上の高齢者は
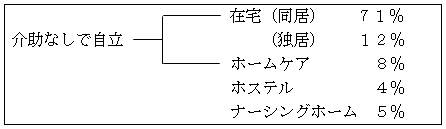
ACAT(Aged Care Assessment Teams):全国に127のチーム、要介護認定が主業務であり毎日、自宅・施設・病院どこでも開催する。8時30分から30分、訪問する場合は面接・評価で45分程度かかる。医療・リハビリ・生活支援・精神的支援の判定もおこない、在宅かホステルかナーシングホームかを決める専門集団で、責任者は医師(多くは老年科医)である。
医師1名・看護婦2名・OT1名・PT1名、他ST・事務等がチームを形成し、中核医療施設が拠点となる。現在の問題点は個人の希望とACATの判定の差をどのように調整するかという点と、高齢者の住居の問題が大きい。より良い評価システムの作成が必要とのことである。
全国に300人の老年科医(専門医)・400人~500人のリハビリ専門医:すべて地域のケアチームに入っている(医師・ソーシャルワーカー・訪問看護・ヘルパー等)。
急性期以降の責任者で、GPとも連携、リハビリの責任者。評価が大切な仕事であり、病院と地域の両方を見ることになりミーティングが多いことが悩み。外来・病棟回診(急性期もリハビリも)・訪問診療(2~3ヶ月おき)・病棟のカンファレンス・地域のカンファレンス等盛りだくさんな業務をこなす。死亡確認はしないこともある。
訪問先について
CSAHS(シドニー中央地区保健サービス)
コンコルド 退役軍人総合病院
バルメイン病院
ロイヤル・プリンス・アルフレッド病院のデイ・ホスピタル
(1)コンコルド退役軍人総合病院
2323人の常勤スタッフ、平均在院日数(4.7日)。日本の代々木の青少年オリンピックセンターのような広大なスペース。建物は古く、改造して使用。今回はショートステイ(痴呆専門)の病棟を見学。
(2)バルメイン病院
100床に212名の常勤スタッフ。1病棟25から26床で構成。
病棟構造:病室4人床(1人8㎡)、食堂・デイルーム・訓練室・バルコニー・トイレ・浴室(シャワールーム)、全スタッフルーム・婦長室・MSW室・ステーション。
平均在院日数:12~16日。(急性期で7日~12日で転院、最大24日間の入院)その後在宅~デイホスピタルへ移行。
(3)ロイヤル・プリンス・アルフレッド病院のデイ・ホスピタル
我が国の本格的リハビリテーション外来とデイケアを併せたもの。60日を限度としている。巡回バス(送迎付き)がある。医師も巡回する。1日に20名で、週に1回~2回、半数以上が在宅で残りはナーシングホーム、ホステル、99%がバルメイン病院の退院者。
ホーンズビィ・クリンガイ病院
シドニー郊外の公立病院、304床でリハビリ病棟がある。その他障害児ケア施設・ナーシングホーム・ホステル・痴呆老人センター等が併設。病棟構造はバルメイン病院の方が良い。リハビリ病棟26床。
在宅ケア(コミュニティケア)について
- 食事の宅配
- ホームヘルパー
- パーソナルケア
- 住宅改造・修理
- レスパイトケア
- 送迎サービス
- 訪問看護
- ヘルスサービス
- 健康審査
- 弁護サービス
- 社会的援助
おわりに
結論から言えば、今年度はCSAHSでの研修を予定している。その理由は、ホーンズビィ・クリンガイ病院の場合は、提供される研修内容がQEC研修と大きな差はなく立地や宿泊施設、研修費用の面で課題があり、またオーストラリア大使館を通しての研修グループ施設から脱会していることも考慮する必要があったためである。CSAHSは、いくつもの病院や施設が連携をとりながら、各々の役割を果たしているグループであり、特に老人ケアの中心的な存在の一つであるバルメイン病院は、市内の中心地から車で10分程度に位置し、3年前まで一般病院であったが、現在では日本の介護力強化病院とリハビリテーション病院を併せたような病院で、その上プライマリーケアにも力を入れているのが特徴である。研修の際には、おそらくこの病院の施設やスタッフが中心になって面倒をみてくれるものと思われる。大変フレンドリーであり、変に研修なれしていないところも好感が持たれた。
CSAHSは、13の施設(ファシリティー)で構成され、急性期から慢性期、コミュニティーケアからロングタームケア、まで、高齢者にかかわるすべてのニードに対応している。個々の施設は、初めから関連していたわけではなく、急性期以降の地域としてのケア体制を整えるために結びついた共同体のようなグループである。そこで下記にあげたようなポイントからCSAHSで来年度からの研修をすすめることとし、オーストラリア視察を終えた。
- 研修スタッフが有能で親切である
- 研修内容やスケジュールに柔軟性がある
- 多くの施設を持ち、高齢者にかかわるほとんどの機能を視察することができる
- 5人ずつの少人数で研修できる
- シドニー市内に研修施設があるため、利便が良い
- 宿泊施設を探すのが容易である
- 自由時間が十分取れる
- オーストラリア大使館が推奨する研修グループである
当会が昭和58年に結成されてから、12年の歳月が流れた。小さな任意団体が、長期間に渡って社会的活動を続けられてきたのは、会員の努力と協力、そして事務局を支えた安藝祐子女子の力だ。
結成当時、老人病院バッシングが巻き起こり、老人保健法の実施で、老人ケアについて関心が集まった。設立に参加した医師は、自ら進んで何とかしない限り、現状を打開することも、老人専門医療の確立が有り得ないことを十分理解していた。
第一に、「襟を正そう」と思った。過剰な診察をやめよう、医療法等の医療関連法規を遵守しよう、脱税行為は絶対しない、入浴設備、食堂などの施設の整備やソーシャルワーカー、理学療法士・作業療法士を採用して質を高めよう、そして最後に老人の人権を守ろうという5原則を話し合った。
さらに、会の運営については、話し合いを基本とし、旅費等の経費については自前とし会費の大部分を社会的活動経費にあて、製薬メーカーなどの一般企業からの寄付は一切受け取らない。入会にあたっては、入会申請時の書類審査に加えて、病院への実態調査を役員が行い、その結果を受けて審査する。選挙時などの政治活動を行わない。そして会員病院名は公表しないことを申し合わせた。
全員、真剣だったし、理念も夢も共有できた楽しい会だ。老人保健施設制度の創設、老人診療報酬などの老人医療制度への提案、入院医療管理料の導入、療養型病床群制度化、老人デイケアや老人リハビリテーションの充実について、直接的間接的に影響を与えてくることができた。
全国老人保健施設協会、全国老人デイケア協議会、日本医療機能評価機構の組織についても、大いに協力してきた。この12年間の老人保健医療分野の動向に深く関わってきたといってもよい。
今、我々の結成当時の希望であった老人病院批判は、顕在化しなくなってきたし、会員病院の施設整備や職員配置の質的向上と量的増加は、まちがいない。しかし、本来の目的である老人専門医療は確立しているとはいいがたい。そして時代は変わった。
会員の中からは「当時の使命は達成されたのであるから、介護力強化病院連絡協議会と一体化してはどうか」という意見もある。結成当時のメンバーは12年歳を取った。若干メンバーも増えたし、物故者もいれば新規入会者もいる中で、この12年間のすべてを知る人は相対的に少なくなっている。
どうするか何日も熟考してみた。そして決断しなければならない時である。幾星霜に新たな大道を求めるか、発展的に散華するかである。感情的には前者だ。しかし後者についても深く考えておくことが必要となっている。
民間の老人病院の理事長、院長、副院長が中心的メンバーであるが、入院医療管理料を採用していない一般病院、精神病院そして診療所の医師もいる。そこには、任意の病院団体なのか老人医療を志す医師集団なのかといったことが曖昧であるという事実がある。12年間に培った有形無形の貴重な財産もある。会員の大多数は、介護力強化病院連絡協議会の会員であり、当会との共催事業も多く、どこまで連絡協議会でどこまでが当会なのかの区別は見えにくくなっている。発展的に散華することは任意団体である以上、いつでも可能だ。しかし、覆水は盆に返らない。公的介護保険や医療法改正の動向は、何があっても不思議ではない。
解散はやめよう。そして老人専門医療の確立を志す医師集団として、介護力強化病院連絡協議会とは別の研究、教育そして社会活動を、新たな大道を求めよう。
折りたたむ...| ×閉じる |